試合結果
New Zealand 41-24 Argentine
New Zealand 893kg
Argentine 940kg
1st Scrum 0:57〜
Argentine陣10m上、New Zealandボールのスクラムです。
組み合った後、スクラムが崩れましたが、反則なくボールアウトとなりました。
セットアップから見ていきます。
今回面白かったのが、フロントローのセットアップが対照的だったのに対して、バック5の動きが非常に似ていました。
まず、対照的だった点から詳しく見ていきましょう。
対照的なのは、HOのバインドする順番です。
New Zealandは3番→1番、対して、Argentineは1番→3番でした。
1番か3番、どちらの密着を優先させるかこのセットアップから凄く分かります。
管理人の拙い記憶を辿ると、Franceは3番から先にバインドをしていました。
ちなみにJapanは、HOがセットした位置に両PRが来るので、HO主導とも言えます。
また、肩の出し方にも違いがありました。
New Zealandは前に肩を出している点に対して、Argentineは横に開く形でした。
スポットコーチングをしていて、たまに思い切り外側に肩を出すチームを見かけるのですが、密着感が弱くなるので、気をつけたい所です。
今回の両チームのセットアップは、参考になるかなと考えてます。
次に、似ていたバック5の動きを見ていきます。
まず、ロックのスタンス(立ち位置、姿勢)がスプリットで膝を浮かせていました。
両膝を地面に着ける場合よりも、早い段階で前に圧力を掛けやすくなります。
重さに差があるため、その差を解消する/活かすために、浮かしていると推測しています。
このセットアップ、映像でNo.8が引いているため、それをすれば導入出来ると考えたら大間違いです。
フロントローとのコネクションを保ちながら、自身もヒットで前に出られる姿勢を作る必要があります。
クラウチの段階から膝を浮かせているため、頭を入れてからフロントローがバインドするまで、前に体重を掛けられません。
後ろに下がれば、バインド時の圧力が小さくなるので、このセットアップを導入する意味がありません。
前に掛かり過ぎても、後ろに下がり過ぎてもいけないので、凄く難しいです。
それでも、多少は前に圧力が掛かるため、フロントロー同士が密着して、ロックも含めたタイト5全員で自立をする必要が出てきます。
映像を観てもらうと、New Zealandが止まっているのに対して、Argentineが微かに動いている事が分かります。
世界レベルでも動くので、導入する際は慎重に考えたいですね。
管理人は試した事ありませんが、密着しながら自立するイメージは凄く浮かびます。
現地でコーチングする機会があれば、導入してみたいセットアップです。
もし試したいチームが居ましたら、連絡ください。
国内では、BL東京が片膝を浮かせていた記憶があります。
ヒット互角、密着感はNew Zealandが良かったです。
それぞれのNo.8のヒット時の動きが素晴らしく、伸びながら沈む事が出来ています。
おそらくNew Zealandが間合いを近くしているので、ヒットスピードと密着で優れば、互角以上に組み合える事が分かります。
スクラムは体重だけでは勝てない、改めて感じたスクラムでした。
Best Scrum 40:17〜
New Zealand陣10m付近、New Zealandボールのスクラムです。
組み合った後、New Zealandが1番主導で前に出て圧力を掛けました。
その結果、Argentineがスクラムを崩したため、コラプシングの反則を取られました。
組み合った後の身体の使い方が凄く上手で、参考になる映像でした。
セットアップから見ていきます。
New Zealandは1st Scrumと変わらず3番側からバインドをしていました。
HOがセットした位置に両PRが合わせている点は違いますが、3番とのバインドを意識したい意図が伺えます。
対してArgentineは、3番からバインドをしていました。
1st Scrumと逆側からバインドしており、特段セットアップに拘りが無い事が分かります。
セットアップに拘ればスクラム強くなるわけではありませんが、相手を粉砕するような強いスクラムはセットアップが確立されています。
バック5も1st Scrumと変わらず前に掛けようとするNew Zealandと後ろに下がり気味だったArgentineと、非常に対照的でした。
低さだけ見ると、Japanの方が格段に低いです。
ただ、まとまりがある分New Zealandのスクラムは強いだろうなと感じてます。
ヒットは互角でした。
組み合った後、New Zealand 1番の左肘の動きに注目して欲しいです。
組んで直ぐに、腕を曲げたのですが、完全に折る事なく、Argentine 3番の上からの圧力に対抗しています。
この段階で、腕を完全に折ってしまうと、左半身が内側に入り込み、スクラムの内側へ巻き込まれて崩れます。
その結果、アングルもしくはコラプシングの反則を取られる事が予想されます。
この肘の動きって凄く重要で、折り畳みすぎると先ほど解説の通りになりますが、畳まないと左肩が前に出ないので、相手の圧力と拮抗する形になります。
また、相手3番が内側に入るスクラムの場合、自身の身体が取り残されやすいです。
マイボールスクラムなので、安定したボールアウトが出来れば良いのですが、ペナルティを取りたい場合は難しいです。
少し折り畳んで、相手3番の姿勢が崩れる/浮き上がるタイミングで、内側に入って圧力を畳み掛けられると、今回のような形で前に出る事が出来ます。
映像を観てもらうと、Argentine 3番の右肩が徐々に下がっている事が分かります。
3番の右肩をいかに下げるか、その際に内側へ逃さないかが1番にとって大切です。
アングル気味になりやすい構造ですが、HOに寄りながら協力して前に出たいですね。
ScrumLoveClubでは、引き続きスポットコーチング受付中です。
もし、安全なスクラムを鍛えたい・基礎を教えて欲しい方が居れば連絡ください。
『スクラムをシンプルに分かりやすく』
日頃からScrumLoveClubをご覧頂きありがとうございます。
今後も精力的に活動しますので、引き続き宜しくお願い致します。
ScrumLoveClubの活動をサポートして頂ける方を募集中です。
OFUSEで応援を送る

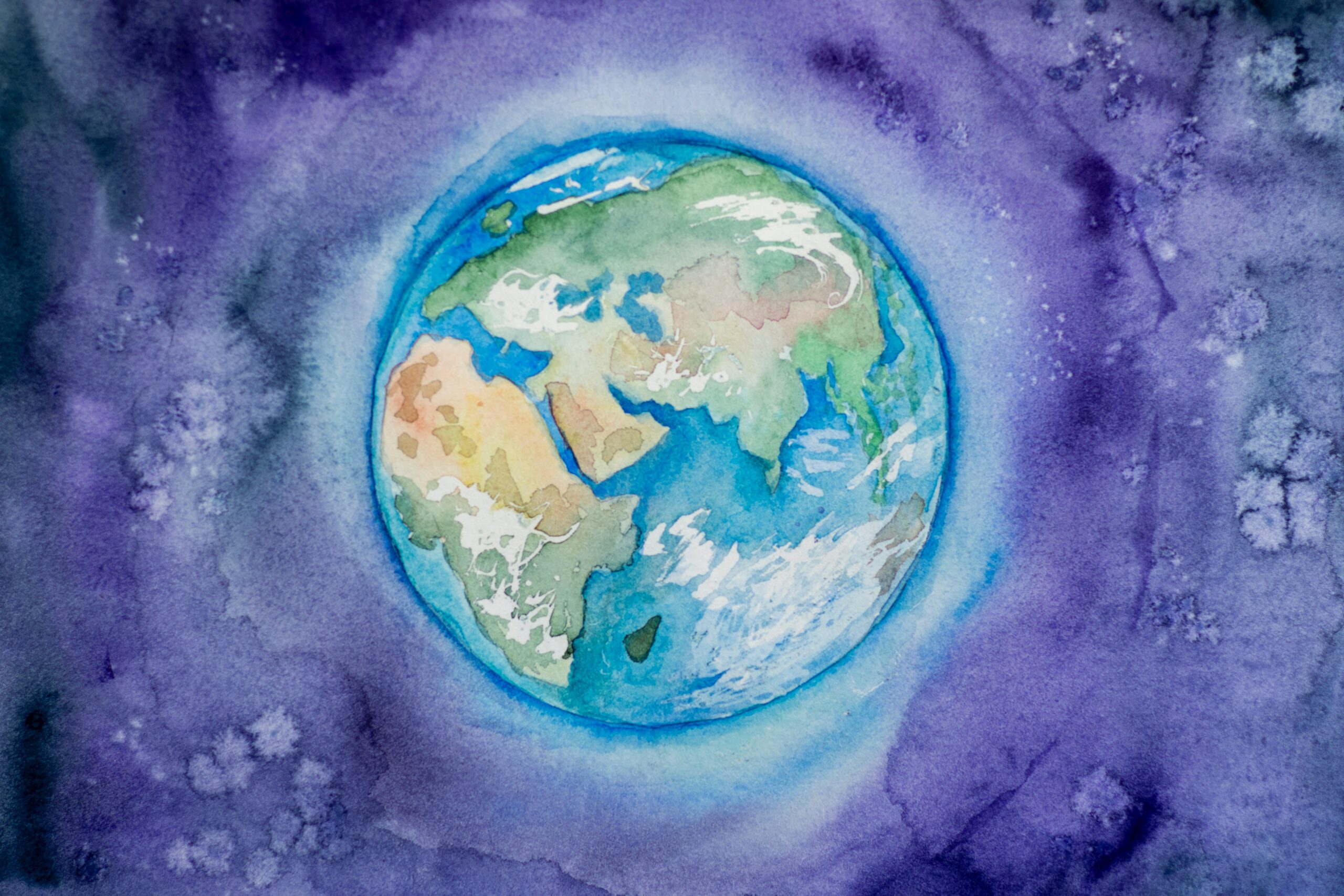

コメント